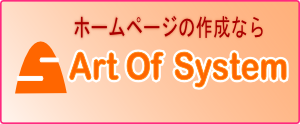共生農場
お年玉特別号・利益を出す株式投資『らせん定期法』
この年末に天に帰った友を思いまとめました。年末31日はお葬式に参列してきました。彼の商売はデフレで年々売上が下がり厳しくなっていました。10年くらい前はベンツのSクラスに乗り、毎年ハワイに家族旅行していました。プレジャーボートも持っていました。お酒が好きな彼は飲み過ぎて肝臓を壊し天に帰りました。お疲れ様でした。
誰にでも思い通りにならない時はある。今まで通りに行かない時は、違うことを何でもいいからやってみるのだ。上手くいかない時は変わるチャンスだ。この新年、自分の力で変わって立ち上がりたい人の役に立つことを願ってこの文章をまとめた。
このらせん定期方が、世の中に広まったときは、株式のらせんの動きが小さくなり、利幅が取りにくくなる。それが10年後なのか、その時が来ないのかはわからない。これからは、痛み分けではなく、楽しみ分けの時代。俺によこせ私に寄こせと争い続けるのはもう終わりにしよう。譲り合いの精神で楽しみを分かち合う時代をこの日本からつくる。共生社会をつくるのだ。この「らせん定期法」は自分の30年間の株式投資の中でまとめたものである。
株式投資で利益を得る2つの基本的な方法
株式投資で利益を得る2つの基本的な方法は、配当金と売買差益である。基本は配当金で利益を得るもの。とは言え、資金が1億円あり、配当利回りが5%で、年間500万円の配当金である。
らせん定期法で1年間52週の内50週で株式の売買をする場合、毎週10万円の売買差益で年間500万円となる。
これをいくらの資金でするのか。500万円の資金であれば50週間毎週2%で毎週10万円となり年間500万円となる。この増えた売買差益を再投資すれば、複利でさらに増えていく。毎週1%であれば毎週5万円の年間250万円である。目標を高く掲げて無理をし、損をしては楽しくない。毎週0.5%の毎週2万5千円で年間125万円でも一般私大の学費くらいにはなる。
500万円の資金で50週間毎週2%の場合に利益を再投資するとどうなるのか。再投資して複利で売買をすると36週で1000万円を超え、50週目には1345万円となる。どこかのタイミングで、手持ち資金の半分を使い配当金のための株式購入をする。それで、売買を毎週しなくても利益が出るようになっていく。
配当金用の資金は、売買差益のための資金にはしてはいけない。売買差益が増えたら配当金を得るための株式を買う。これを繰り返すことで、売買をしなくても配当金だけで大きな利益が得られるようにしていく。
どんな、配当金銘柄を選ぶのか
配当金をさらに再投資して増やす。つまり複利で増やすということ。複利が効いているのが目につくまでに15年くらいかかる。15年以上は、配当金を出し続けてくれる会社の株式を選ぶ必要がある。できれば配当金を増やし続けてくれる会社がなお嬉しい。その時の社会情勢やシステムにもよるが、土管ビジネスは配当金が高めで安定していることが多い。電気ガス水道。これからはネットのインフラも社会生活に必要な基本的な設備となる。生活を支える土管である。
証券会社のデータやYahooファイナンスのデータを検索し、過去の配当性向や会社情報も調べたうえで、好みの会社の株を保有し、配当金を得るのだ。
資金が少ない場合は、「らせん定期法」で売買益を得る。
らせん定期法の勝てる原理
売買差益で利益を出すらせん定期法で勝てる原理は次のとおりである。利益を出すためには、どの銘柄をいつ買って(売って)いつ売る(買う)のかが、明確にルール化されている必要がある。
沢山稼ぐためには、マーケティングの法則通り、1.客単価(狙う差額)を増やす。つまり、長い周期で大きな差益を得る。2.客数(取引金額)を上げる。3.購入頻度(取引回数)を増やす。この3つの内のできるところを増やす必要がある。
精神的な負担が少ない方法で取引をする
株式の売買差益を狙いつつ損をするのは、精神的な負担や葛藤に負けるからである。精神的に負けると実際の売買でも負けるのである。取引を抱えているという事は、精神的に負荷を抱えているということ。
株式売買で利益を出し続けるためには、精神的な負担が少ないことが必須。楽しく株式投資をするのである。ゲームのように楽しむのだ。その為のやり方と心構えが、らせん定期法である。
仮に買って3営業日以内に売ると決めていた場合で、買った日にマイナス10000円になり翌2日目にブラス1000円ななった時に売りたかったら売るのだ。耐えられない不安なら売って氣楽になるのだ。不安を抱えていると、余計なことを考える。考えなくていいことを考えて無駄なエネルギーを使うのだ。そして判断ミスもしやすくなる。
であれば、売って手持ちをなくすのだ。仮にその時マイナスであったとしても、それ以上のマイナスにはならないのである。それから、冷静に株価の推移をみて、どうすればよかったのかを考えるのだ。銘柄選定、買うタイミング、売るタイミング、取引量、どこで躓いたのか確認するのだ。そしてその経験を次に生かすのだ。
株式投資でうまくいかない原因は、買う銘柄選定、買うタイミング、売るタイミングを間違うからだ。間違ったときには、すぐに損切りすることが重要である。損切を出来ないと損が膨らむ。それを避けるための定期である。自分の思惑やニュースで投資期間を延ばさないのだ。当初決めた期間で売り切ることで、損を抱えないようになる。これが大切。勝てると確信できた時だけ買う。それでも間違うことがある。
らせん銘柄選び1、日柄
この宇宙の基本原則がらせん運動だ。小さな原子レベルから大きな宇宙まで、すべてらせん運動だ。河川も水源から河口まで、直線距離の約3倍となっている。
売買の差益を得るのが目的である。その差がわかりやすい銘柄を選ぶのだ。比較的周期が安定しているものがわかりやすい。まず、月足で1サイクル何か月なのかを数えてみる。底から次の底までの月数を数えてみる。
ここでは日経平均で見てみる。すると月足でも大回りと小回りの周期があることがわかる。大回りの底が、2008年10月、2011年11月、2014年4月、2016年6月、2018年12月、2020年3月だ。月足大回り1サイクルが37か月、29か月、26か月、30か月、15か月と、15から37か月である。
小回りは、2016年6月以降、2016年11月、2017年4月、2017年9月、2018年3月、2018年12月、2019年8月、2020年3月だ。月足小回りが5か月、6か月、5か月、6か月、9か月、9か月、7か月だ。最近は5か月から9か月である。但し、これが絶対ではない。4か月や10か月や11か月もあるかもしれない。この月足の底が、配当金を得る株式を買うタイミングでもある。
次に週足で数えてみる。週足にも大回りと小回りがある。大回りの底が、2018年3月30日、2018年12月、2019年8月、2020年3月と月足の小回りと同じである。
週足の小回りの底は、2018年3月30日、2018年7月6日、2018年10月26日、2018年12月28日、2019年3月29日、2019年6月7日、2019年8月9日、2020年1月8日、2020年3月19日、2020年8月7日、2020年10月30日だ。週足小回りは、14週、16週、9週、13週、10週、9週、22週、10週、20週、12週だ。
それでは、次に日足で数えて下さい。証券会社のホームページやYahooファイナンスで日経平均の日足を見て数えて下さい。
ここでは、わかりにくい所はあえて数えない。人によって数えやすいところが多少違う。自分が明確にわかればそれでOKである。あなたが認識しやすいサイクルの銘柄を探すのだ。
らせん銘柄選び2、取引量
常に株式が流通していることが大切。新興市場は、取引量にバラツキがあるので、売りたい時に売れなくなる。売りたい時に売れる可能性が高い東証1部の銘柄で売買する。出来高があり流通性があるものなら東証ETFもあり得る。流通性が低い銘柄は、寄り付き以外に取引が無い日もあり得る。日中に売りたくても売れない、ということが起こり得るのだ。
現在私が日経平均の売買を考える時、上がると見立てた時は、日経平均レバレッジ上場投信(1570)、日経平均ブル2倍上場投信(1579)、この2つ。下がると見立てた時は、日経平均ベア2倍上場投信(1360)である。この組み合わせであれば、信用取引の空売りをせずに下がると見立てた時にも取引をすることができる。
選んだ銘柄の3つの周期を俯瞰し、数えて売買のタイミングを計れるのかを確認する
選んだ銘柄の月足を見て、現在の流れの方向性が上なのか下なのかを見極め判断する。底から底の期間を数えるのだ。そして、今はどのあたりに位置しているのかを判断する。次に週足を見て、現在の流れの方向性が上なのか下なのかを見極め判断する。月足と週足の上下の見極めが異なることもある。月足は上を目指していても、週足は下を目指している時もある。
次に日足の方向性を判断する。また、日足で1サイクル上がり何日、下り何日かを数える。特に上りは最低何日かかるのか直近10山くらい数える。
値上がりを期待する時は、月足と週足も上げ基調の銘柄にする。その方が上げの期間が長く、値上がり幅も大きくなる傾向がある。月足や週足が下げ基調の時に日足の上げを狙う場合は、買ってから売るまでの日数を1日から3日、もしくは買った日のうちに売る。長く持たない。
買うタイミング仕入れが大事
どんな商売でも仕入が悪いと儲からない。また、販売価格を間違えても利益は残らない。その仕入れ値となる買うタイミングはいかに計るのか。それは、日柄とボリンジャーバンドで計る。日柄とは先に数えた日数である。ボリンジャーバンドとは自分でネット検索してください。ボリンジャーバンドの「-1σ」「-2σ」「-3σ」まで下がったタイミングを買うタイミングとする。
過去の日柄を見る時に一緒にボリンジャーバンドのどのラインまで可能性があるのか確認しておく。ボリンジャーバンドも100%ではない。「-2σ」の予想が、現実は「-1σ」ということも、その逆もある。時には「-3σ」もある。相場は他人である。自分の思惑通りには動かないものである。だから売るタイミングを定期にして、損をしにくい取引にする。大きく儲けるよりは、減らさず少しでもいいから増やすようにする。
売るタイミングは定期にするから塩漬けがない
仕入れから売却まで基本は3日以内とする。長くて5日。短ければ当日もある。特に日足の上がりが1日で翌日に同じくらい下がる銘柄の場合は、朝買って14時台には売るということもあり得る。
底で買い天井で売りたい。が、間違って途中で買った場合は、利益が少なくても手じまいする。間違ったら手じまいする。長く抱えないということが、損をしない秘訣である。年末は一旦手じまいすることもある。
マメに取引ができない時
忙しくて日中日足を見ての売買ができない場合は、月足で長期間とする。2~3年の長期保有の1取引での売買差益を狙うということ。この場合は、波形の形を見る、上がっていく波形のパターンが何通りかあるので、その形にはまっていることが必須。波形を勉強してください。
長期間保有するので、底打ちの確認をしたい。前回の底よりも直近の底の方が高値であることで、底打ちしたと判断する。その為に、急激に上がる波形の場合は、確認をしてから買うことができない場合もある。底から1回上がった後、月足のロウソク足で陰線1、2本をつけて小動きになったら買うタイミングである。しかし株式投資に絶対はない。
年末の事例
日経平均は一度下がってから上がると思っていた。それで、2020年12月21日に1360を買った。3日間と想定していたら、翌22日に日経平均は下がった。売りそこなったのである。しょうがないので翌23日にほぼ買値で損切である。間違ったらすぐに切るのである。これを損切りしていなかったら、29日に大きなマイナスである。
その後28日の値動きで、これはすぐに上がりそうだと感じ、1570と1579を買ったところ、翌29日には714円の上昇となった。当初5日以内(新年6日迄)で売却と考えていたが、上がり方が急であり、なおかつ年末年始で休場もあるので、大納会の日に売っておしまいである。これが現実。
新年どこかで今よりも数百円は下がる可能性が高い。その時には日経平均の日足が25日線や「-1σ」付近まで下がる可能性が高い。あまり下がらない場合は、「+1σ」かもしれない。あるいは新年に2020年の高値を抜くことがあり、「+2σ」や「+3σ」となった場合は、そこから下がることもある。相場は他人であり自分の思惑では動かない。その時がきたら、またチャレンジしていく。
何か副業をするよりは、自分にとってはとても簡単である。株式の売買をしたことがない人は、まずは机上で数サイクル試してみてはいかがだろうか。その際は必ず紙に書くなど記録すること。日経平均が3万円を超え4万円になろうが、逆に2万円になろうが、利益を出し続けるのだ。そういうゲームである。サイクルを見極めて待って買い、3日以内に売るゲーム。腕が上がると利益も上がる。
皆様が楽しく豊かな人生を歩まれることをお祈りしています。
免責事項
この文章の内容や数字は誤っている可能性もあります。本文章で株式投資を勧めるものではありません。また株式投資の利益を保証するものでも助言でもありません。記載内容を参考にしてあなたが株式投資をするときは、自己責任での投資です。本文章の情報により、皆様に発生あるいは誘発されたいかなる損害について、本文章作者、及び全ての関係者は一切その責任を負いません。本文章はいかなる金融商品を勧誘するものでも、投資情報を提供するものでもありません。私の事例を簡単に紹介したものです。
ファイル名の末尾に「_xxx」等を付けて無効化すると、baserCMSの基本のコメントフォームを呼び出すことができます。