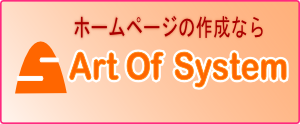薬剤師すみこの玄米生活
おひつのご飯の秘密

こんにちは。残暑が厳しいですね。夏らしいことをやっていない方にとってはチャンスですよね。ここで楽しく夏の思い出を作ってもらえればと思います。
炊飯器が発明されたのは戦後のことですが、それまでわたしたちはどのようにしてご飯を食べていたのでしょうか?朝、かまどで炊いたご飯をおひつに移してそこから食べていました。おひつには保温効果はないですので、冷や飯を食べるということになります。朝はかまどで炊いたホカホカの白米を食べる。昼はおにぎりにして作業の合間に食べる。夜は冷や飯のまま食べるか?野菜と一緒に混ぜて雑炊として食べるといったことをやっていたようです。1日1食はホカホカの白米を食べていたというのが歴史となります。
冷や飯には「レジスタントスターチ」が含まれています。消化酵素に抵抗する(=レジスタント)でんぷん(=スターチ)という意味です。消化酵素に抵抗するので、消化吸収されずに大腸まで届きます。大腸では腸内細菌がたくさんいますので、彼らのエサがやってくるのです。それを食べて元気になるので、腸内環境が活性化されます。腸内環境が活性化されることでスムーズなお通じが得られます。また、いい腸内環境は毒素が減りますので、これにより肌状態がよくなります。便秘の改善が肌状態をよくするのはこういう理由になります。1日1回は効率よくエネルギーを作るためにホカホカの白米を食べて、残り2回は冷や飯を食べて腸内環境を活性化させていたというのが歴史になります。
食物繊維とは消化されない糖質全てを言います。でんぷんに限らず様々な糖質がありその総称が食物繊維です。消化されない糖質は大腸へ届きそこで腸内細菌のエサとなります。これにより腸内環境が活性化されます。様々な糖質がありますが、水溶性と不溶性とに分けられます。不溶性は繊維状になっていることが多く、この繊維に中性脂肪などがからめとられてそのまま大腸へ運ばれています。
玄米には食物繊維の他にビタミンなどの栄養分が合わせて含まれています。消化されない糖質が多いことから、歴史通り1日2回食べているのが今やっている玄米生活です。
おひつのご飯に保管されている冷や飯ですら理にかなっているということなのですね。